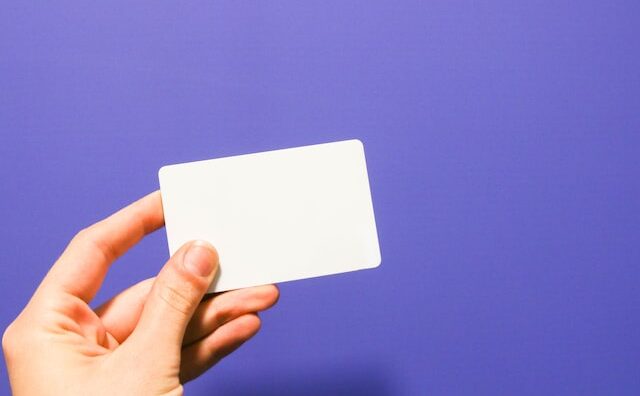こんにちは。好きなことでゆるく働き、都心ミニマルライフを楽しむもふもふです。
かっこつけているわけでもなんでもないのですが、私は他人に嫉妬という感情をもったことが、おそらく一度もないと思います。
友人にこの話をすると、そんな人いる?嘘でしょ?と若干引かれるので、自分はこの世にあるあたりまえの感情を知らないんだなあと思っています。
ただ、嫉妬するなら、とりあえず自分でやってみよ。というのが、私の方法です。
今回は、「嫉妬=自分の憧れ。なら、とりあえずやってみよう!」についてお伝えします。
私はなぜ嫉妬をしないのか?

自分がこの世にある当然の情緒に触れてこなかったのは、なぜだ?と考えてみました。
結論は、
自分が欲しいと思うものを持っている人に、たまたま出会ったことがないから
でした。
そう、私はたまたまその経験がなかっただけなのです。
夫が本をだしたことで気づいた
たとえば、夫が数年前に本を出版しました。
本の内容はビジネス系のものだったのですが、ある時ふと「もしこれが小説だったら、自分は嫌だったかも?」と思ったんですよね。
どうやら、身近な人が小説家だったら、私は嫉妬をするみたいです。 謎すぎる。
自分が小説家になりたいのかというとそうでもないのですが、どうやらフィクション×文章の表現力というものに、自分が憧れているようです。
そこから、たとえば大学の時にクラスから芥川賞作家登場!なんてことがあったら、と想像しました。
うぬぬくやしい!となった自分に笑えました。
嫉妬とは、自分の欲求を具現化するツールなんですね。
そして、おそらく多くの方と異なるのは、そこから私が実際に何本か短編小説を書いていることかもしれません。
短編小説、書くの楽しかった
嫉妬があるということは、自分の願望がそこにあるということですよね?
なので、深く考えることもなく、とりあえず自分も小説を書こうと思いました。
自分で言うのもなんですが、私は自分のこの思考と行動がけっこう好きです。
うじうじする間もなく「いったんやってみよ。」となる単純さって、私は健やかさだと思うんですよね。
小説を書くというと、どこかに応募するの?何のために書くの?と聞かれそうですが、行動の意味付けこそ、意味がありません。
何のためにやるのか?を考えるのは、全て無意味なのです。
意味をつけるとしたら、
ほんの少し、やってみたいと思った。
だけで良いのです。
短編小説を書くのは楽しかった!
私はペットシッターをしているので、長年見続けた都心に住む人々の暮らしや、富裕層界隈で巻き起こる事件をまとめた短編小説にしました。
で、これをどうしたかというと、推敲に推敲を重ね、突然満足して放置しています。
どこかに応募するには実話すぎるので修正しなければいけないし、そもそも小説家になりたいわけでもないので、書いたら満足しました。
ちなみに「発表していないけど神作」というわけでもなく、夫や友人の評価は、絶賛というにはほど遠い「ま、なかなかの出来だね。」という程度でしたよ。
他人に自作の小説を見せるなんて、厨二か?と夫には言われましたが、私は自分のことが大好きなので、特に恥ずかしいとも思いません。(それより、添削してもらうほうが大事。)
このように、自己肯定感が高く、自分への期待値が低いと何かと便利です。
実際に、この時は酷評されなかったというだけで、書いてよかった〜!とホクホク顔をしていましたよ。
みなさんにお伝えしたいのは、私がやばい人という話ではなく、こちらです。
- 嫉妬をすることは、あなたがやってみたいこと。
- やりたいことなんて、この程度のことで全然いい。
要は嫉妬なんかする前に、意味などなくても、自分の手を動かした方が楽しいよってことです。
まとめ
以上、「嫉妬=自分の憧れ。なら、とりあえずやってみよう!」についてお伝えしました。
私が今好きなことでゆるく働いているのは、まさにこういう小さな遊びを次々楽しんだ結果だと思っています。
よく「副業への種を蒔く」などというと、試行錯誤や努力みたいなイメージを持たれるかもしれませんが、少なくとも私の場合は全然違います。
自分が楽しいと思うことを、やりたいと少しでも思った時に、ただやってみる・楽しいなら続ける、というだけなんですよね。
このブログも、あの時の小説と同じような感覚ではじめ、現在はたまたま皆さんに読んでいただくことになり、ささやかながら収益をいただいているという感じです。
そういうわけで、嫉妬起点でもなんでもいいから、とにかく自分で行動してみると何かと面白いよ。という話でした♪
【関連】よろしければこちらもどうぞ。